正しいファイル名のつけ方って?基本的なルールやコツを紹介

日々の業務で増え続けるファイルや資料。特に企業では、複数人で同じデータを扱う機会が多く、「ファイルが見つからない」「最新版が分からない」といった小さなトラブルが積み重なると、業務効率や情報共有に大きな影響を与えます。
そんな問題を防ぐカギが「正しいファイル名のつけ方」です。この記事では、企業の現場でもすぐに使えるファイル名の基本ルールやコツ、よくあるNG例などをわかりやすく解説します。
- 1. ファイル名の重要性
- 1.1. 正しいファイル名をつけるメリット
- 1.2. 正しいファイル名をつけないと、どうなる?
- 2. 正しいファイル名のつけ方
- 2.1. 基本ルール
- 2.1.1. 日付を入れる
- 2.1.2. 内容を具体的に記載
- 2.1.3. 文字数は短めに・記号に注意
- 2.1.4. 表記ルールを統一する
- 2.2. NG例
- 2.3. コツ・注意点
- 2.3.1. 命名ルールは最初に決めておく
- 2.3.2. バージョン管理は明確に
- 2.3.3. 略語や個人だけが分かる表現は避ける
- 2.3.4. 定期的に見直し・整理する時間を設ける
- 3. フォルダ名の付け方は?
- 4. パソコンのファイル整理術を学ぶなら
- 5. 正しいファイル名のつけ方をチェック
ファイル名の重要性

日々の業務や生活の中で、私たちは多くのデジタルデータを扱っています。写真、書類、PDF、スプレッドシートなど、ファイルの種類や数は多種多様。
そんな中で、「どこに何があるのか」を一目で把握し、必要なときにすぐ取り出せる状態にしておくために欠かせないのが、ファイル名のつけ方です。
正しいファイル名をつけるメリット
正しいファイル名をつけることは、デジタルデータを効率よく管理・活用するうえで非常に重要です。誰が見ても内容がすぐにわかる名前をつけておけば、ファイルの検索や共有、整理がスムーズになり、作業効率が大幅に向上します。
また、履歴管理や引き継ぎも円滑になり、作業ミスや情報の取り違いを防ぐ効果もあります。適切なファイル名は、単なる“ラベル”以上の意味を持ちます。それは、情報管理の基盤であり、作業効率やチーム連携を左右する大切なポイントでもあるのです。
正しいファイル名をつけないと、どうなる?
正しいファイル名をつけないと、必要なデータを探すのに時間がかかり、作業効率が低下します。「最終版」「新規」など曖昧な名前では中身が分かりづらく、誤って古いファイルを使用するリスクも。チーム内での情報共有や引き継ぎにも支障が出やすくなり、トラブルやミスの原因になります。結果として、業務の属人化や混乱を招きやすくなるのです。
正しいファイル名のつけ方

ファイル名は、ただの“ラベル”ではなく“情報を管理するための鍵”です。どんなに便利なツールやフォルダ構成があっても、肝心のファイル名が適当では意味がありません。ここでは、誰でもすぐに実践できるファイル名のつけ方の基本ルールや、失敗しがちなNG例、スムーズに運用するためのコツや注意点を、具体的に解説します。
基本ルール
ファイル名をつけるには、まず押さえておきたい“基本ルール”があります。誰が見てもわかりやすく、後からでも迷わず探し出せるようにするためには、シンプルで一貫性のある命名が不可欠です。ここでは、実践しやすいファイル名のつけ方の基本を、具体例を交えてご紹介します。
日付を入れる
ファイル名に「20250410」のような日付を含めることで、作成順に並べたり、履歴を把握しやすくなります。定期的な資料管理にも有効です。
内容を具体的に記載
ファイルの中身がすぐに分かるよう、「見積書_株式会社〇〇」など、用途や対象を具体的に書くと、検索性と共有性が高まります。
文字数は短めに・記号に注意
長すぎる名前や「/」「*」「?」などの記号は、保存エラーや他の環境での不具合の原因に。シンプルで扱いやすい名称を心がけましょう。
表記ルールを統一する
日付の書き方(例:yyyymmdd)、区切り記号(例:「_」「-」)などを統一することで、一覧表示した際に整理された印象になり、目的のデータファイルやフォルダを探しやすくなります。
NG例

どんなにファイルを整理しようとしても、間違った名前のつけ方をしてしまうと、かえって混乱の原因になります。ありがちな失敗例を知っておくことで、同じミスを防ぐことができます。ここでは、実際によく見かけるNGファイル名とその問題点を紹介します。
・新規.docx
「新規」だけでは何のファイルなのか判断できず、複数存在すると区別がつきません。時間が経つと用途も忘れがちになるため要注意です。
・ああああ.pptx
仮でつけた名前のまま保存すると、後から自分でも中身が分からなくなります。他人が見た場合はなおさら意味不明で扱いに困ります。
・2025/04/10*資料.docx
スラッシュ「/」やアスタリスク「*」など、一部の記号はファイル名として使用できません。エラーの原因になり、保存や共有ができなくなります。
・会議資料最終_修正_最新版_本当の最新版.pptx
修正を重ねるうちに名前が複雑になり、結局どれが最新版か分からなくなります。明確なバージョン表記の工夫が必要です。
コツ・注意点

正しいファイル名をつけるためには、基本ルールだけでなく、運用面での“ちょっとした工夫”も大切です。日々の業務で無理なく継続するためのコツや、意外と見落としがちな注意点を押さえておきましょう。
命名ルールは最初に決めておく
個人でもチームでも、まずは「どういうルールで名づけるか」を決めることが重要です。
たとえば以下のようなルールが考えられます。
例)・日付表記は「YYYYMMDD」で統一(例:20250410)
・区切りには「_(アンダースコア)」を使う
・固定の並び順を設ける(例:日付_内容_担当名)
あらかじめルール化しておくことで迷わず名づけられ、作業の属人化も防げます。
バージョン管理は明確に
同じファイルに何度も修正が入る場合、ファイル名でバージョン管理をしておくと便利です。
例)・報告書_20250410_ver1.docx
・報告書_20250410_ver2.docx
特に「修正前に戻りたい」「どこが変更されたか比較したい」といった場合に、履歴のトラッキングが容易になります。
略語や個人だけが分かる表現は避ける
自分には分かっても、他の人には伝わらない略語や記号、コードなどは避けるのがベターです。
例)NG:「mtg(会議の略)」「shd(スケジュールの略)」「xx(とりあえず使われる記号的な略例)」など
OK:「会議」「資料」「見積書」など内容が具体的にわかる表記
チームでの共有や将来的な引き継ぎを考慮し、“第三者目線”で命名することが大切です。
定期的に見直し・整理する時間を設ける
ファイル名を整えていても、時間が経てば情報が古くなったり、使わなくなったファイルが溜まったりします。週1回や月1回など、定期的なファイル整理の時間をスケジュールに組み込むことで、快適な状態を保てます。
フォルダ名の付け方は?
フォルダ名とファイル名は、どちらもデータを整理・管理するために重要ですが、それぞれの役割や命名の考え方には少し違いがあります。以下に、主なポイントを整理してご紹介します。
| 項目 | フォルダ名 | ファイル名 |
| 目的 | 情報の分類・グループ化 | ファイルの中身を明示する |
| 表す内容 | 年月、相手先、業務カテゴリなど | 日付、内容、バージョン、関係者など |
| 文字数 | 短めでもOK | 内容が分かる程度に具体的に |
| 共通ルール | 記号制限・表記統一などは同じ | 同左 |
実際には、フォルダ名とファイル名の基本ルールはほぼ共通で使えます。大事なのは、役割に応じて“何を表すのか”を意識してつけ分けることです。フォルダ名は“カテゴリ”、ファイル名は“中身の説明”を意識して命名することで、より整理されたストレスのないデジタル環境が実現できます。
パソコンのファイル整理術を学ぶなら
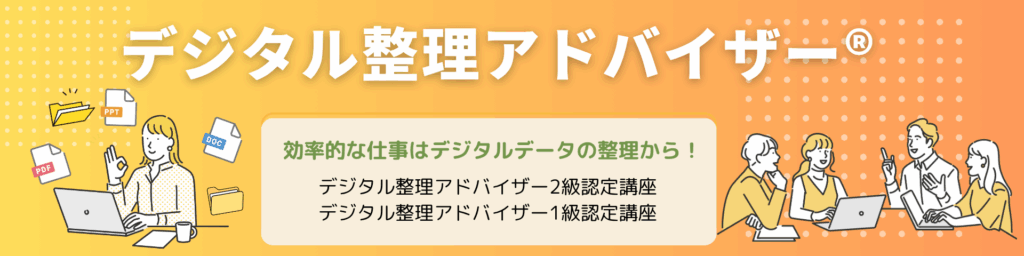
フォルダ名やファイル名を整えることは、デジタル整理の第一歩。でも、長年積もったデータやフォルダ構成がごちゃごちゃだと、どこから手をつけていいか分からない…という方も多いはず。そんな方には、デジタル整理アドバイザー®認定講座がおすすめです。パソコンの中を効率よく整理し、日々の業務や生活の質をぐっと高める方法を学べます。
「どんなフォルダ構成にすればいい?」「社内ルールに合った命名方法を決めたい」「資料を効率よく共有・管理したい」…
経験豊富な講師がそんなお悩みも解決します。デジタル整理でお困りの方は、ぜひ一度ご受講ください!
正しいファイル名のつけ方をチェック
ファイル名のつけ方ひとつで、情報の探しやすさや業務効率が大きく変わります。特に企業では、チームでのファイル共有や引き継ぎが日常的に行われるため、ルールのない命名は混乱やミスの原因になります。日付・内容・バージョンなどを明確にしたファイル名は、検索性や管理性を高め、企業全体の生産性向上にも貢献します。
個人レベルの意識改革はもちろん、組織として命名ルールを整備・運用していくことが、これからの情報管理における重要な一歩です。
アナタも『デジタル整理®』を学びませんか?
このコラムを書いた人:有賀 照枝
(株式会社デジタル・ファイリング・ラボ 取締役/デジタル整理アドバイザー®認定講師)

