【ファイル名のルール】基本的なポイントを解説
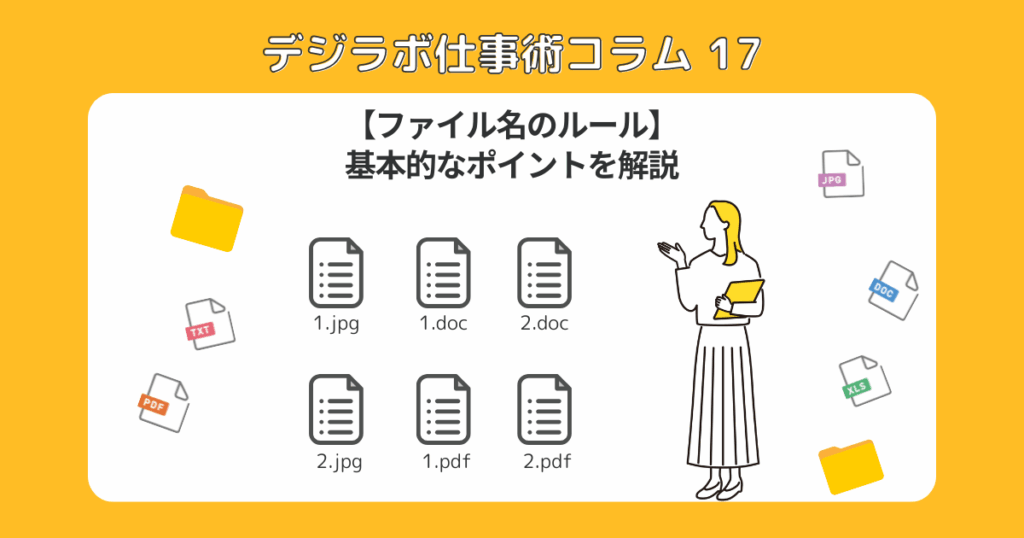
パソコンやクラウドの中で、「あのデータ、どこいったっけ?」と探し物に時間を取られていませんか?
ファイルをきちんと整理したつもりでも、同じような名前の書類がずらっと並んでいたり、「最終」「最新版」「本当の最新版」なんてファイルができていたり…。
これ、実は「ファイル名のルール」が決まっていないことが原因なのです。
今回は、ファイル名のルールをどう決めるか・どう守るかというテーマでお話しします。
「センスじゃなく、仕組みで片づける」――そんなデジタル整理の第一歩です。
ファイル名のルールの必要性

「別に好きな名前でつけても困らないでしょ?」と思う方、いませんか?
確かに、ひとりで作業しているうちは問題ないかもしれません。
でも、数が増えてきた瞬間から、一気にカオスになります。
ファイル名にルールがないと、以下のようなことが起こります。
- 目的のデータを探すのに時間がかかる
- 誤って古いファイルを使ってしまう
- 共有相手が中身を開けるまで内容がわからない
- クラウド上で同名ファイルが上書きされる
つまり、情報が「整理されていない状態」になってしまうのです。
紙の書類なら、表紙に「見積書」と手書きしてファイルするだけでわかりますが、デジタルでは
名前こそが“表紙”の役割。
見た目では区別がつかないからこそ、名前のルールが命なのです。
また、ルールがないと、保存したはずのデータが見つからないというトラブルも起こります。
これは、「保管した情報を“管理”する仕組み」がない状態。
だからこそ、日常の業務効率を守るためにも、ルールづくりが必要なのです。
ファイル名のルールを決める際のポイント

「ルール」と言っても、堅苦しく考える必要はありません。
要は、“誰が見ても同じようにわかる”ようにすること。
ここでは、ファイル名をつけるときの基本的な方法を解説します。
情報の順番を決める
まずは、どんな順番で情報を並べるかを決めましょう。
たとえば「日付→内容→取引先」のように。
例:20251006_提案書_株式会社デジラボ.pdf
このように並べておくと、並び替え(ソート)したときに時系列順に整列でき、あとから探すのがぐっとラクになります。
さらに、ファイルの種類(提案書・見積書・契約書など)を明記すると、同じフォルダ内での分類もスムーズになります。
日付は「西暦+月+日」で統一
ファイル名の日付は、「YYYYMMDD」形式が基本。
「2025年10月6日」なら「20251006」と書きます。
「10.6」「10月6日」などの表記ゆれを避けることで、自動的に日付順で並ぶんです。
使用禁止文字に注意
WindowsやMacでは、ファイル名に使えない文字があります。
「/」「\」「:」「*」「?」「“」「<」「>」「|」などが代表例。
フォルダごと共有する場合、他のOSでエラーになることもあるため、使わないのが鉄則です。
ファイル名は短く・わかりやすく
長すぎるファイル名はトラブルのもと。
共有ドライブでは途中で省略表示されて「結局どれがどれ?」状態になります。
20〜30文字以内を目安に、簡潔にまとめましょう。
例:
× 「20251006_整理収納フェスティバル2025出展者説明会用配布資料最終版ver3.pdf」
○ 「20251006_出展説明会資料_03.pdf」
「最終版」「最新版」禁止令
誰もがつけたことがあるこの呪いの言葉、「最終版」。
気づけば「最終」「最終版」「最終の最終」「ほんとに最終」…。
これでは、どれが本当に最新なのか誰にもわかりません。
解決策はシンプル。日付で管理すること。
または、バージョン番号(v1, v2, v3)で進行状況を示す方法もおすすめです。
例:
- 20251006_提案書_v1.docx
- 20251010_提案書_v2.docx
こうしておけば、誰が見ても一目で最新がわかります。
社内・チーム全員で統一する
個人のセンスではなく、チームの共通ルールとして決めることが重要です。
フォルダごとに「命名ルール表」や「README.txt」を入れておくと、あとから見ても迷いません。
ルールを社内で浸透させるには?

特に企業や組織では、複数人で同じフォルダを使う機会が多いため、ルールの統一が欠かせません。
せっかくルールを作っても、「あなただけが守ってる状態」では意味がありません。
では、どうすれば社内に浸透するのでしょうか?
まずは“小さなチーム”から始める
いきなり全社統一!はハードルが高いです。
最初は自分のチームや部署など、身近な範囲でテスト運用してみましょう。
実際に使ってみて、使いにくい部分を修正してから全社展開する方がスムーズです。
マニュアルを“読む”ではなく“見る”にする
文字だけのガイドラインは、なかなか読まれません。
できれば画面キャプチャ付きのサンプル集を作るのがおすすめです。
「このフォルダではこう名前をつける」など、実例ベースで共有しましょう。
「守れない人」を責めない
新しいルールは、すぐには浸透しません。
間違えた人に注意するより、「こうした方が後で探しやすいよ」と伝えるほうがずっと効果的です。
「ルール=縛り」ではなく、「時短の味方」として伝えていきましょう。
ファイル整理術を学ぶなら
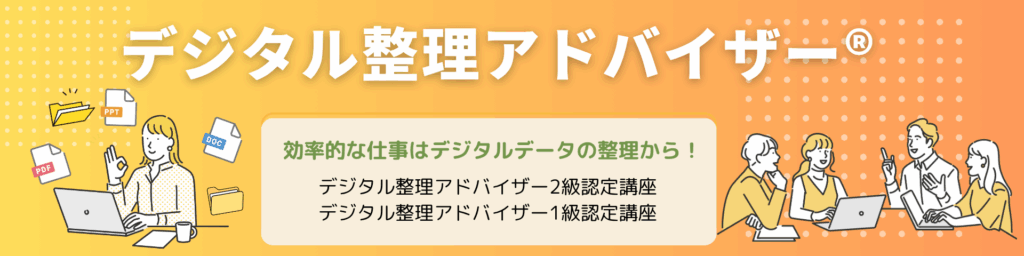
「ファイル名のルールが、大事なのはわかったけど、実際にどう決めたらいいの?」
そんな方におすすめなのが、デジタル整理アドバイザー®認定講座です。
この講座では、
- ファイルの分類方法
- フォルダ構成の考え方
- ファイル名のルール策定の実例
- チームで共有するためのルール設計
などを、実務ベースで体系的に学べます。
「整理収納アドバイザー」は“モノの整理”、
「デジタル整理アドバイザー®」は“データの整理”。
どちらも“探す時間を減らして、使う時間を増やす”ためのスキルです。
講座修了後には、自分だけでなく、チーム全体の働き方も変わります。
ファイル名のルール策定は重要
ファイル名のルールは、単なる“名付けのマナー”ではありません。
それは、情報を見える化し、探す時間を減らすための整理術です。
ルールを決めることは、「未来の自分へのやさしさ」。
そしてそれをチームで共有することは、「働く仲間への思いやり」でもあります。
今日から少しずつでも構いません。
「ファイル名に“意味”を持たせる」――そこから、あなたのデジタル環境が変わり始めます。
アナタも『デジタル整理®』を学びませんか?
このコラムを書いた人:福永 恵(株式会社デジタル・ファイリング・ラボ 代表)
デジタル整理®の力で、誰もが快適に働ける環境を。
デジタル整理アドバイザー認定講座草案者の一人。
整理収納アドバイザー、ScanSnapプレミアムアンバサダー。
ファイル名にも人生にも、“迷わないルール”を。

