ファイル共有の主な方法を解説!それぞれのメリット・デメリットも
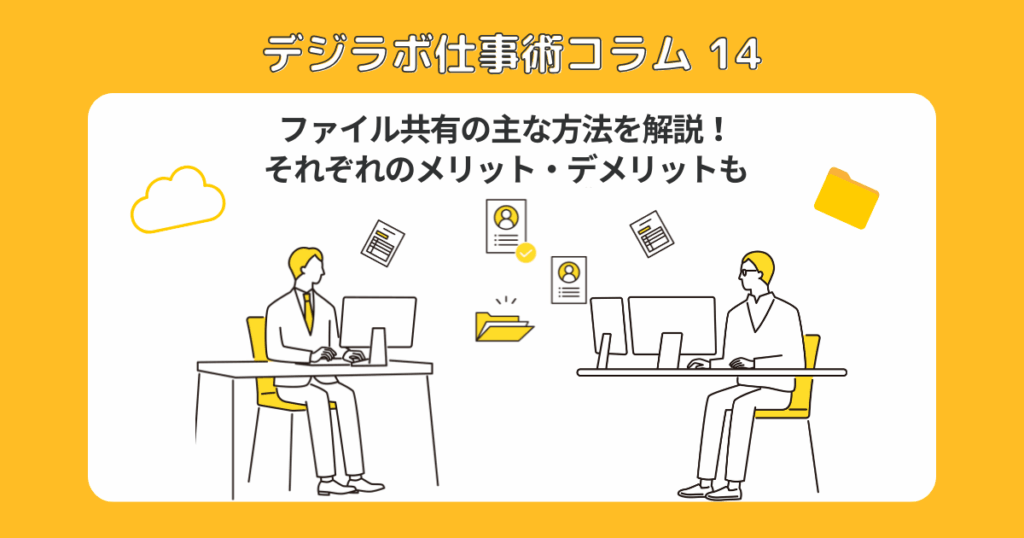
仕事やプライベートで作成した資料や画像、動画などのファイルを、職場のチームのメンバーや友人と共有する機会は多くありますよね。
その共有方法は一つではなく、用途や相手の環境によって最適な手段が異なります。
今回は、ファイル共有の主な方法と、それぞれのメリット・デメリット、注意点についてお伝えします。
ファイル共有が必要な場面

ファイル共有は、単にデータを送信するだけでなく、共同作業や情報共有を円滑に進めるための重要な手段です。具体的な場面としては以下が挙げられます。
- 業務資料のやり取り
社内や取引先とプレゼン資料、企画書、契約書などを共有するケース - 共同作業
複数人で同じドキュメントを編集しながら作業するケース - 写真・動画の配布
イベント写真やPR動画を関係者に配布するケース - 大容量ファイルの送信
メール添付では送れない容量のデータを渡すケース
これらを共有するケースでは、スピード・安全性・操作のしやすさが重要なポイントになります。
ファイル共有の主な方法

ファイル共有には、フィジカルで物理的な媒体を使う方法から、デジタルでインターネットを経由する方法までさまざまな選択肢があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
USBメモリ
USBメモリは、パソコンのUSBポートに差し込んでデータを保存・取り出しする、手のひらサイズの以下の記憶媒体です。
ネット環境がなくても利用でき、シンプルでわかりやすい方法です。
●メリット
ネット環境が不要
操作が簡単で誰でも使える
大容量データも高速で移動可能
●デメリット
破損・紛失・盗難のリスク
ウイルス感染の可能性
物理的な受け渡しが必要
メール
メールでのファイル共有は、添付機能を使って相手にデータを送信します。
ビジネスからプライベートまで広く普及、定着している手段といえます。
●メリット
メールアカウントがあればすぐ送れる
メッセージと一緒に送信可能
特別なツールをインストール不要
●デメリット
添付容量に制限(一般的に数MB〜25MB)
誤送信による情報漏えいのリスク
大量のファイル送信には不向き
ファイル共有サービス
ファイル共有サービスは、大容量のデータを一時的にクラウドにアップロードし、相手にダウンロードURLを送って受け渡す方法です。
GigaFile便やFirestorageなどがよく知られているサービスです。
●メリット
大容量ファイルを一時的に送信できる
相手は会員登録不要で受け取れる場合が多い
有効期限を設定できる
●デメリット
一定期間でデータが削除される
無料版は広告表示や容量制限あり
公衆Wi-Fi利用時のセキュリティリスク
クラウドストレージ
クラウドストレージは、インターネット上のサーバーにデータを保存し、URLや共有機能を使って他のユーザーと共有できるサービスです。
代表的なものにはGoogle Drive、Dropbox、OneDriveなどがあります。
●メリット
インターネット環境があれば様々なデバイスからアクセス可能
複数ユーザーで同時編集が可能
自動バックアップ機能がある場合が多い
●デメリット
ネット環境が必須
無料プランは容量制限あり
誤ったアクセス権限設定による情報漏えいリスク
ファイル共有に関する注意点

ファイル共有には多くのメリットがありますが、トラブルや情報漏えいなどのリスクを回避するには、次のような注意点を押さえておく必要があります。
- アクセス権限の管理
必要なユーザーだけがアクセス、また編集できるようにするなどの設定をする。 - パスワード設定
重要なデータには必ずパスワードを設定し、別ルートで伝える。 - 期限付き公開
不要になったら共有リンクを削除し、公開期間を限定する。 - セキュリティ対策
ウイルスチェックや暗号化機能を活用する。
ファイルを共有する際には
ファイル共有の方法は複数あり、それぞれに適した用途があります。
例えば、小容量データならメール、大容量データの一時送信ならファイル共有サービス、大容量データの共有や共同作業ならクラウドストレージ、といった具合です。
大切なのは、「安全・確実・効率的」に共有できる方法を選ぶことです。
当社が主催する「デジタル整理アドバイザー®2級認定講座」では、ご自身のパソコン内のデータ整理について、「デジタル整理アドバイザー®1級認定講座」ではチーム内のデータ整理について主にお伝えしています。
ファイル共有をスムーズにトラブルなく行うためにはデータ整理は必須です。
プライベート、また業務でのデータ整理にお悩みの方は、ぜひご受講ください!
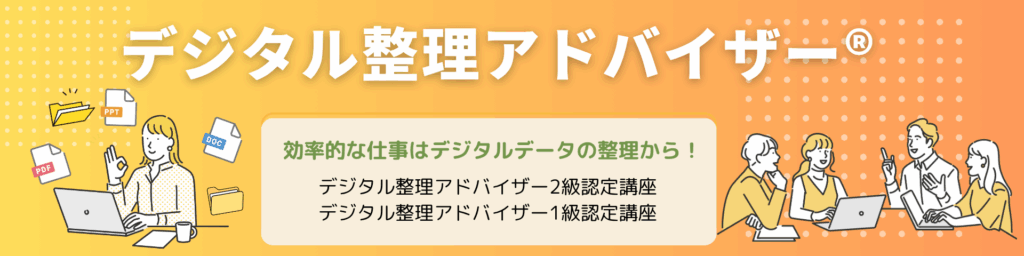
アナタも『デジタル整理®』を学びませんか?
このコラムを書いた人:梶岡 ルミ子
(株式会社デジタル・ファイリング・ラボ 取締役/デジタル整理アドバイザー®認定講師)

