AIを活用したデータ整理とは?おすすめツールや注意点など
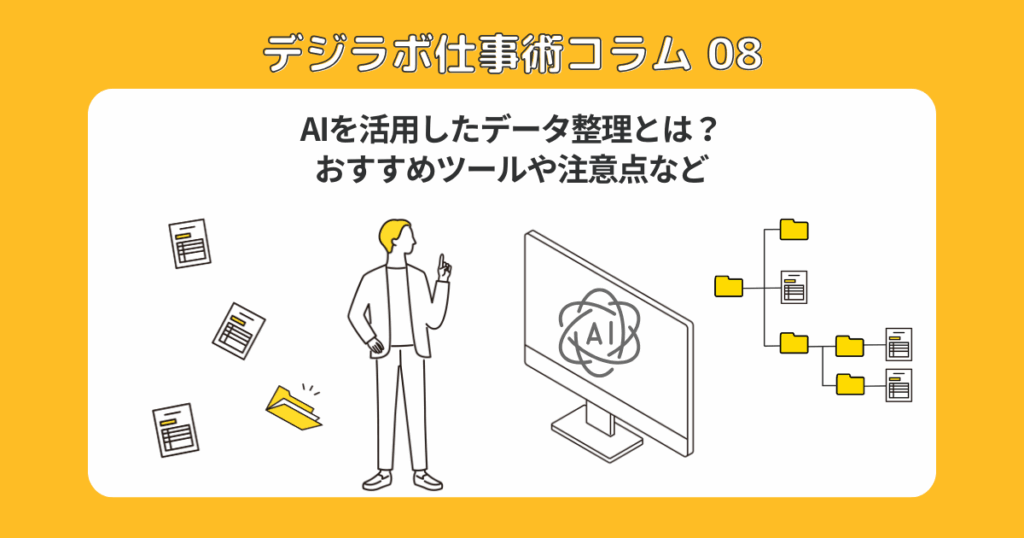
アルバニアではついに「AI閣僚」が誕生しました。政治の世界にまでAIが導入されるなんて、もうSFではなく現実の話。
それなら私たちの仕事や暮らしの中に、AIが入り込むのも当然ですよね。特に「データ整理」の分野では、AIの活用がどんどん進んでいます。
今回は、AIを活用したデータ整理の基本、便利なツール、導入するときの注意点をわかりやすく解説します。
AIを活用したデータ整理とは?
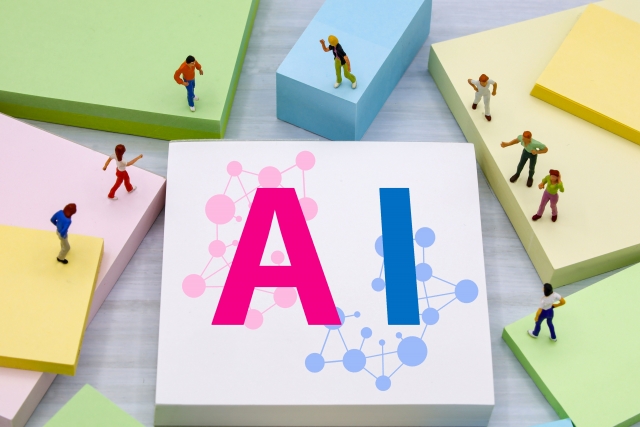
AIを活用したデータ整理とは、人工知能の学習・分類・理解の機能を利用して、膨大なデータを自動で整理・管理することを指します。
従来は人間が作業として行ってきたフォルダ分けやファイル名付けといったデータ整理も、AIなら一瞬。
たとえば、
- 写真から「犬」「旅行」「会議資料」などを自動で分類
- 文書の内容を理解して要約を作成
- PDFやWordなど異なる形式のファイルを整理してまとめる
といったことが可能です。つまり、これまで人が時間をかけていた雑用も、AIを使えば“頼れる秘書”を手に入れたのと同然なのです。
■ AIを活用するメリット
時間の節約
これまで何時間もかかっていた仕分け作業が、数分で終わります。浮いた時間は本来のビジネスに使えますね。
正確さの向上
誤字や似た名前によるミスを防ぎ、ファイルの形式や中身を正しく把握してくれます。
学習して進化
一度の誤分類も学習材料に。次は改善され、どんどん精度が上がっていきます。
【AIを活用したデータ整理】おすすめツール・方法

AIと聞くと難しそうに感じる方も多いですが、身近なサービスにすでに組み込まれています。ここからは、AIを活用したデータ整理でおすすめの代表的なツールを紹介します。
ChatGPT
自然言語処理に優れ、文章の整理や作成が得意。
- 会議録を読みやすい形式に要約
- メール文を自動で作成
- キーワードごとにテキストを分類
AIが内容を理解して整理するので、作業効率が一気にアップします。
Google Drive(AI機能)
DriveではAIが「必要そうなファイル」を提案。
さらにGoogleフォトと連携すれば、写真を自動で分類してくれます。
「去年の研修資料」「旅行の写真」などを検索すれば、AIが瞬時に探し出すのです。
Notion AI
ノートアプリNotionに搭載されたAIは、情報整理が大得意。
- 会議ノートをアクションリストに変換
- 長文を短く要約
- データベースを効率的に分類
チームで導入すれば、ビジネスの情報共有がぐっとスムーズになります。
Evernote + AI機能
保存したノートにAIがタグ付けや分類を追加。
「去年の請求書」や「誰の発言か」といった情報を瞬時に検索できます。異なる形式のファイルでもまとめて扱えるのが強みです。
その他おすすめツール
Microsoft Copilot:Excelでのデータ作成や整理を自動化
Otter.ai:会議録の文字起こし&要約
Grammarly:文書の理解・整理・校正に強み
AIを活用したデータ整理の注意点
便利なAIですが、導入時にはいくつかの注意が必要です。
情報漏えいリスク
AIツールに入力したデータが外部に保存される場合があります。機密情報の取り扱いには特に注意を。
完璧ではない
AIの理解は万能ではなく、誤分類や誤解釈も発生します。最終チェックは必ず人間が行いましょう。
コストの管理
無料利用の範囲を超えると、月額課金が意外と高額になることも。
ビジネス導入ではコストパフォーマンスを見極めましょう。
AI任せにしすぎない
AIは「勝手にいい感じにしてくれる魔法」ではありません。
むしろ、自分たちの業務に合った方法をルールとして指示しなければ、かえって混乱を招くこともあります。
例えば「営業資料は日付順」「写真は顧客別」など、自分たちにとって使いやすい形をAIに覚えさせることが重要です。
AIを活用したデータ整理を取り入れてみては

AIを活用したデータ整理の本質は「AIに従う」のではなく、「AIをこちらのルールに従わせる」こと。
正しく指示を出せば、AIは便利で頼れる相棒になります。
弊社が運営するデジタル整理アドバイザー®認定講座では、AIツールそのものの導入や操作を教えるわけではありません。ですが、いざAIを導入して活用しようとするときに欠かせない、フォルダ構成や分類ルール、ファイル名の付け方といった基礎的な考え方を体系的に学べるのが特徴です。
AIを使いこなすためには、まず人が「どう整理したいか」という土台を持っていることが必要不可欠。
AIはあくまでアシスタントであり、主役は私たち自身です。自分たちが使いやすい形式でデータを管理する考え方を身につけることこそが、AI時代のデータ整理のゴールなのです。
AIデータ整理をチェックしてみよう
AIを導入する前に、まずは現場のデータ整理の環境が整っているかを確認しましょう。
- AIに指示できるような、自分たちのルールを決めているか
- 異なる形式のファイル(PDFやWordなど)が混在しても整理できる基盤があるか
- 情報漏えいリスクやコストへの配慮を、あらかじめ検討しているか
- AI任せにせず、人の目で最終チェックする仕組みを考えているか
これらが整っていれば、AI導入後もスムーズに活用できます。
逆に「整理ルールがあいまい」「仕組みがまだ固まっていない」と感じる方は、まずデジタル整理アドバイザー®認定講座で基礎から学んでおくことをおすすめします。
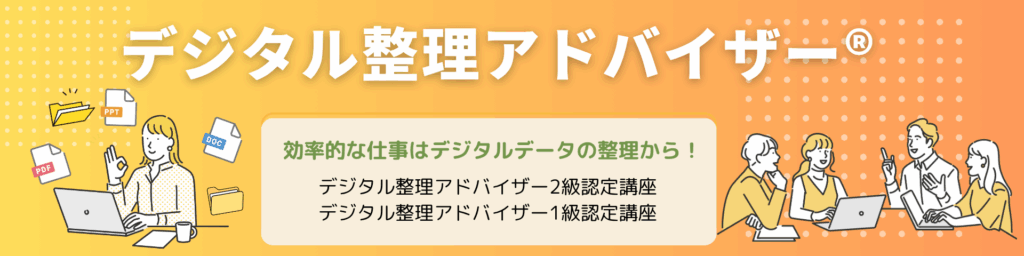
AIに「おやつの時間も作って」とは頼めませんが(笑)、データ整理の強力な助っ人になってくれるのは間違いありません。
探し物にかかる時間を減らし、ストレスを手放して、人とAIが共に作業を進める快適なデジタル環境を手に入れましょう!
このコラムを書いた人:福永 恵(株式会社デジタル・ファイリング・ラボ 代表)

